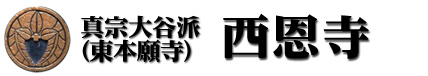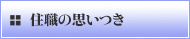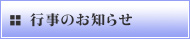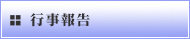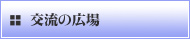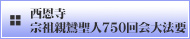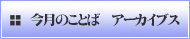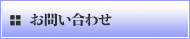「経糸はよく、横糸を貫きたもつ」
「経」といふは経なり。経よく緯を持ちて匹丈を成ずることを得て、その丈用あり。→「経」というのは、経糸です。経糸は、横糸をよく貫きたもち、布を織り上げ、そうして織った布には、それぞれのはたらきがあります。
善導大師は、「お経(教え)とは、経糸である」と言われます。私たちの人生を一枚の布に譬えられます。布は経糸をしっかり張ることによって、横糸を渡すことができるそうです。経糸がしっかり張られていないと横糸をどれだけ渡しても、その布は用きを成さない、完成しないということです。
改めて、自分には経糸が張られていないことを教えられました。その場しのぎの、一貫性のない人生であると炙り出されたことです。
仏教では人間のことを「機」と表現します。それは、「はずむ」ということです。「縁を生きる」われわれは「はずみ」の存在です。どこへ転ぶか、どんな自分に出会うのかは分からないのです。だから不安です。だからこそ、その私を荷負う―責任主体こそ経糸としての「経」(教え)であるというのです。
その経糸(教え)は、同時に「よく横糸を貫きと持つ」という用きがあると言われます。横糸とは、私が刻んできた歴史であり、歩みであります。しかしその重ねてきた時間は、「いたずらにあかし、いたずらに暮らして年月を送るばかりなり」(蓮如『御文』)と指摘されるように、重大なことがあっても「喉元過ぎれば熱さを忘れる」で、毎日の生活に追われて、忘却し続けているのです。大震災も、原発問題も、大切な人の死も、すべて自己関心の中で「通過」させてきたのです。無関心、「個人的」生き方に終始しているのです。その「通過」の人生を立ち止まらせ、問題を思い起こさせ、課題として保たせる用き、促しこそ、経糸であるお経(教え)であるというのです。
お経(教え)に出遇うことによって、個人性、閉鎖性を破り、関係性、人間性を取り戻していくのではないかと思います、
今年は戦後70年、この国の方向転換が行われました。しかし、またそのことも時間と共に忘れてしまう日常の中で、その課題を思い起こさせ、向き合い直す視点こそお経(教え)であります。
今年も間もなく終わります。皆様は、どんな歩みを刻んでこられたのでしょうか?
年の瀬に改めて、教えを聞き、仰ぐという生活の
大切さ感じましたのでお聞きをいただきました。
ありがとうございました。
(西恩寺住職 池田徹)