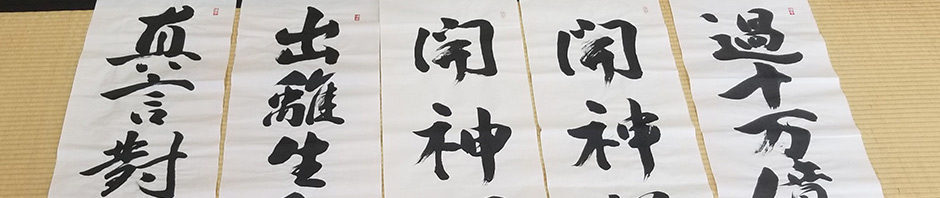池田義男氏にご寄稿をお願いしました
≪開基・喜受≫のことども
「熱僧・池田喜受」—真宗西恩寺の胤を、ここ桑名の地に落としたのは、間違いなく在家出身のこの人だった。裸一貫立ち上がって、寺創建の事業を走り抜けたこの人の情熱のすさまじさは筆舌に尽くしがたい。創建60有余年の西恩寺の、どの瓦にも柱にも、この人の血涙がしみ込んでいるといっていい。
生まれは石川県小松在の奥深い山里だが、名にし負う真宗王国北陸だった環境がおのずと信徒熱を高めることになった上に、父親が近在きっての篤信の妙好人だったことも大きく働いた。いわば、襁褓(むつき)のころから南無阿弥陀仏に囲まれて育ち、人となった。結婚して一族ともども桑名に移ってからもその熱は冷めることなく続いた。妻つきとの間に八人の子どもに恵まれたが、祖母いよの縁で寺参りに浸ってきた末っ子勇諦(俗名・勇)が、血がそうさせたのか幼くして自ら「ボク、お坊さんになりたい。なる」と親に告げたことで、就学前の息子の出家得度から「寺創建」へと、喜受の信徒熱は思いもかけぬ方向へ飛躍していくことになった。
かくして、寝ても覚めても「寺づくり」への情熱に駆り立てられて、喜受は一途に猛進した。格別の資産なし、おカネなしの中から、生業の傍ら、伝手を求め、寒暖を押して学生の息子を伴に一軒一軒奉加帳を持って懇志を願って回り、また木材の寄進を懇請して足を棒にして山村を歩いた。三間に及ぶヒノキ材を荷車に乗せ、七里の山道を汗を絞って引いてきたことも一再ではなかった。息子たちがこの苦闘の手伝いをして汗を流した。投げられたサイ。否も応もなかった。するしかなかった。走り回るよりほかなかった道。
十代の勇諦も置かれた事態を全身でよく理解し、己の進むべき道をしかと決めて、周囲の期待に応えるべく、学業の合間を縫って法縁に出座し、親鸞布教の道を学びつつ、一途に宗門修行に励む明け暮れに突き進んだ。
その姿に喜受もまた、時間をつくって法座めぐりを続けて耳を傾け、同行同信の士たちと「御文」に親しみ念仏を絶やさず「三部経」の勉強にいそしんだ。この情熱が寺創建を機縁として、息子を追っかけて出家得度の道へと進んでいくことになった。
かくて、少しずつ賛同の士を増やしつつ、篤信の信徒の支援と懇志に支えられ、かつ一家あげてのエネルギーを傾けた、長い血の汗と涙の果実として、この地にささやかな本堂が建ったとき、「真宗西恩寺」の一歩が目に見える形で世の中へ踏み出したといえようか。昭和の世が敗戦の焦土からようやく抜け出して20年代半ばにさしかかろうとしていた時期であった。
****** ******
思えば、八世蓮如ゆかりの、あの吉崎御坊の伝承に息づく越前加賀の国境いに近い地にルーツを持つ真宗大谷派西恩寺は、そのまま開基・池田喜受の「宗祖讃仰熱」を土台にして、その情熱をそのままこの桑名の今に持ち込んだ「熱い寺」といえるのではないだろうか。
当初、町の人々からは「寺を建てる? ここに」と驚かれ、時にあきれ返られながら、ひたすら汗を流して「我が道」を往った開基・喜受。こんな人物は、恐らくこれからの時代も、なかなか二度と現われてはこないのではないだろうか。
西恩寺開基は、そんな気のする一代の稀僧・熱僧ではある。
喜受撞くや 久遠の鐘の 響く春
合掌
2017年1月 池田 義男 敬白
(喜受四男、中日新聞社参与)