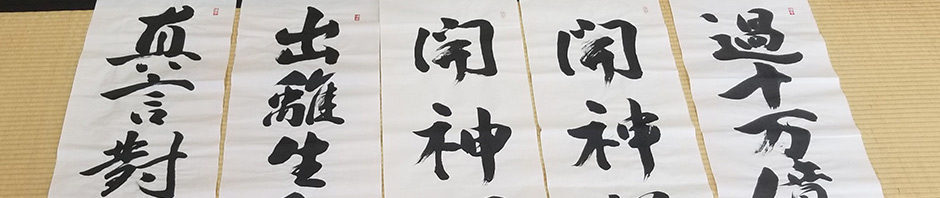●「一つには、必定地獄と聞きながら、うぬぼれ心にだまされて、堕ちるわが身ということを、ほんにいままで、知らなんだ」。これは結局、自分の今日の足下に気付かせて頂く、それこそ地獄行きだと聞かされながら、自分の自惚れ心に騙されて生きておる今日の自分だ、ということを、ほんに今まで知らなんだ。
●「二つには 不定(ふじよう)のいのちをもちながら、よもやよもやで日を送る、今宵も知れぬいのちとは、ほんにいままで、知らなんだ」。これを読みます度に思われることは、私たちは、生は必然、死が偶然、そんなふうな気持ちで生きておるんです。ところが事実は逆なんですね。死は必然であり、生は偶然である。たまたま今日もまたいのちを頂いた。ところが私たちの日常意識というのは、まったく逆さまで、生きているのは当たり前、死ぬのはたまたまだと。私たちは錯覚してしまっておる。そういう自分のあり方というものが、仏法を聞くことによって、今宵も知れぬいのちとは、ほんにいままで、知らなんだ。
●「三つには 皆さん後生(ごしよう)は大事やと、ひとには言うて聞かすれど、わが身の大事ということを、ほんにいままで、知らなんだ」。いやぁ、これはほんとに厳しいと言いましょうか、これは松岡なみさんから言えば、ほんとに仏法を深く聞かせて頂いていくと、無意識のうちに今度は人に聞かせ屋になってしまうんですね。自分の問題ということを何か忘れてしまって、自惚れと言いましょうかね、教え手になっていく、そういう自分を懺悔していらっしゃる言葉でもないかと思うんですね。
●「四つには よくよくお慈悲を聞いてみりゃ、たすける弥陀が手をさげて、まかせてくれよの仰せとは、ほんにいままで、知らなんだ」。これは阿弥陀如来のお心というものを表しているのですが、「任せよ」と聞かされておりながら、任されない自分の分別・はからいの日常生活があるということなんですね。親鸞聖人のお言葉に、「念仏をしながら、他力を頼まぬなり」というお言葉があるんですけど、ほんとにそうだと思うんですね。そのことに気付かれたところで、いよいよ任せてくれの仰せを聞いていかれた姿じゃないかと思いますね。
●「五つには いつもお礼はいそがしく、浮世ばなしに気が長い、かかる横着者ということを、ほんにいままで、知らなんだ」。これもほんとに耳の痛い厳しいお言葉です。この「いつもお礼はいそがしく」ということは、朝晩のお参りをすることです。それは忙しく、せかせかと急いで、そして浮き世話に気が長い、と言うんですね。ほんとにこれは身に摘まされることですわ。手を合わせるのはチャカチャカとして終えて、どうでもいいような世間話には、時間忘れてうつつぬかしておるという、それを懺悔しておるんですね。
●「六つには 難かしむつかしと歎いたが、おのれが勝手にむつかしく、していたものということを、ほんにいままで、知らなんだ」。自分の分別・はからいで、私たちは聞いていますから、だから仏法を聞くと言いましても、自分の考えを押し立てておるのであって、仏様からどう願われておるのかという、それを、全然聞いていないんですね、聞こうとしないんですよ。これがいつもすれ違うわけですわね。だから難しいということで、わからんということで、結局、自分と自分で難しくわからんようにしているんだという、そういうことを、おなみさんは痛んでおるんだろうと思うんですね。これを読みますと、松岡なみさんの真剣な聞法体験、わかりたいし、わからんし、という、そのジレンマを潜られたことが滲み出ている響きが致します。
ところで私がこの一連の歌に、何故注目するのか。それは誰しもが本気になって仏法に向き合いますと、必ず通る道行きですけれども、仏法は難しい、分からんという問題の壁です。その確信の一点として私は、仏法がわかるということは、如何なる質の出来事なのか。その一つを問わずにいられないのです。その点がこの松岡なみさんの歌から、一筋の光を感ずるところであり、またその点を子ども心なりに感じた、私自身の子どもの頃の嬉しさだったようです。
近代の科学的実証主義の洗礼を受けた現代人は、この目で見ることができるもの、この耳で聞くことのできるもの、この手で触れることができるものだけが実在して、そうでないものは存在しないし、また価値もないとしているようであります。人間が理性を持つものである限り、合理性は尊重されねばならない基本であることは言うまでもありません。かと言って逆に、合理性を至上とする人間中心主義の発想には、それ以上の問題を感じるのは現代であります。それは現代のあらゆる領域での危機的な状況がそれに由来していることを否めないからであります。そうした人間中心主義の発想、傲慢さを問い返す時、「不合理なるが故にわれ信ず」というこの言葉が、かえって極めて謙虚な宗教的姿勢を語るものと感じられてなりません。その意味でこの不合理は、親鸞聖人の教えに照らせば、むしろ私たちの分別・はからいを超えた新合理の意味で用いられたものと言われずにいられません。その「超えた」と今申しました、その内実は、私たちの理性の立場、つまり理性至上のあり方と、反対の理性無視のあり方との両極をどちらも主とするという理性の立場の外に立つことを意味しています。ここに私たちは、親鸞聖人が「自力のはからいを捨てて、他力に帰せよ」と言われるいる一点をよくよく聞かねばならないのです。
では、「はからいを捨てる」ということは、どういう体験なのでしょうか。およそ私たち人間が、言葉を持つ存在であることは、すべての経験が言葉によることを意味しています。その意味で私たちの分別・はからいとは、言葉だと言いましょう。であれば、「はからいを捨てる」とは、必然的に言葉を超えることでなければならないのでしょう。言葉を超えるとは、かえって言葉以前の事実に立ち返ることでしょう。私たちは、分別以後で生きていますけれども、現前のいのちの事実は、分別以前に根差した生、生きてある現実であります。ですから私たちが、本当に積極的に生きる原点を先輩は、「思いに死んで事実に生きよ」と喝破されています。そうした言葉以前の事実に回帰した、立ち返った自覚を、親鸞聖人は、「不可称不可説不可思議の功徳は行者の身にみてり」(高僧和讃)と歌われています。今、不思議とは、ああかこうかと、いろいろ頭で思案、はからっていたことが、実際事実そのものに触れた時、今までの自分の思いが吹っ飛んで、ああそうか、と驚く・感動、それを不可思議と説かれるのです。ああなったら、そうなったらという分別をしている限り、確かな歩みは出てまいりません。今こうなっている、これだったという事実に気付く時、初めて現前の事実と向き合っていく確かな歩みが始まるのではありませんか。
(つづく)
(平成20年10月26日)ラジオ放送より